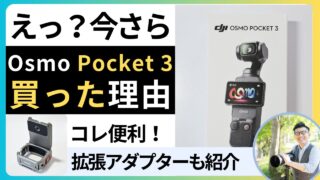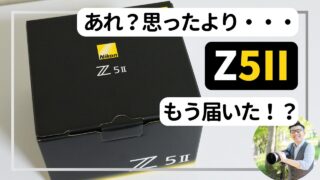こんにちは、Jimaです。
今回はセンサーサイズのお話でAPS-Cを選ぶと、コスパ良く機材を揃えることをが可能な方の特徴を説明してまいりますね(^^)
この記事を見るメリット
- センサーサイズで悩んでる方
- APS-Cの魅力を知りたい方
- コスパ良いカメラの選び方を知りたい
- センサーサイズ別の特徴
- フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズ
- 暗さ耐性、ボケ感、広角撮影
- サイズ感(小型軽量)
- レンズのラインナップについて
まとめ:暗い環境や広角で撮らないなら APS-Cはコスパ良し

突然ですが・・・
画角の感覚を把握するために
ここでセンサーサイズ別のクイズをしてみましょう。

それでは答え合わせですが・・・
正解はAがAPS-Cで、Bがフルサイズです。

センサーサイズの話
- Nikonの一眼レフは大きく2種類
- フルサイズ(FX機) / APS-C(DX機)
- イメージセンサーの大きさのこと
- センサーはカメラの中でもめっちゃ重要な部分
- センサーが小さいとカメラの小型・軽量に貢献
- センサーが大きいと多くの光を取り込みやすい
- 結果、白トビや黒つぶれが少なくなる
- 階調豊かな表現が可能
- 焦点距離もフルサイズとAPS-Cで異なる

望遠撮影に最高
- APS-Cの焦点距離が伸びる特性を活かせる
- 連写が強い機種なので、遠くの動き物に強い
- 野鳥やスポーツ撮影に最適
- 私はD750などで野鳥を撮る D500が羨ましい
- 200-500mmなら、300-750mmとなる

センサーサイズの違い【5点】
- 画角が変わる
- APS-Cは約1.5倍 寄った(望遠)になる
- 逆に広角レンズの特徴が弱くなる
→ 広角撮影が好きならフルサイズが良い - 選ぶレンズ 注意が必要(35mm?50mm?)
- ボケ感
- 焦点距離が変わるので被写界深度が変わる
- 結果、画角を同じにしてもボケ感に差が出る
- 階調 / 暗所性能
- フルサイズは多くの光を取り込める
→ 結果、階調表現が豊かで暗所性能が高い
→ 暗い環境/明暗差が激しいならフルサイズ
- フルサイズは多くの光を取り込める

センサーサイズの違い【5点】
- サイズ感(重さ)
- センサーサイズに比例してボディが小型化
- APS-Cは必然的に機能も削るので小型化
- 小型軽量は正義、機動力と性能を意識すべし
- 交換レンズ
- フルサイズに比べラインナップが多い
- ガラスの大きさ、質に比例して低価格
- 重ねて伝える、焦点距離に要注意

センサーサイズで悩んでる方へ
- 画角、ボケ感、階調の差を意識して決めるべし
- 広角撮影の頻度は?
- 超広角のレンズを使えばOK
- ボケ感はどの程度求める?
- f1.4 / f1.2 などのf値の魔法での表現もアリ
- 暗い環境での撮影頻度は?
- フルサイズはAPS-Cの魅力を知りたい方
- 広角撮影の頻度は?
- コスパ良いカメラはAPS-Cに多い
- センサーサイズは価格に直結しやすい
- APS-Cは数万円~10万円代が多い
- フルサイズは10万後半~70万など
- 本格的、マニアックなものはもっと高い
- 機能面やブランドでも価格が変わる
価格とフルサイズの特性が必要かで決めればOK
念のため、欲しい特徴のレンズ有無をチェック
つまり・・・
画角
ボケ感
階調の差 など
センサーサイズの特性を理解し
ご自身の撮り方からAPS-Cでも
問題がないかを見極めるべし
そうすると、結果的にコスパ良い買い物ができます
私がフルサイズ(35mm)を使う理由
- D780使用、ただフルサイズ絶対主義者ではない
- D3000やD5000系統のカメラも使う
- Z50やα6400はめっちゃ欲しい
- 小型・軽量でしっかり撮れる機種は魅力的
画角
- 広角撮影にやっぱりフルサイズの画角は心強い
- 広角時はAPS-Cとの差は凄く感じる
- APS-Cで24mm使うなら36mmぐらいになる

ボケ感が強く出せる撮り方ができる
- 同じ被写体を同じ画角で捉える場合・・・
- APS-Cに比べてフルサイズは被写体に近寄る
- 結果、被写界深度からボケ感が強く出せる
- f1.4などの開放f値が低いレンズを使えばOK
- ただ、解放f値が低いレンズは高い・・・

階調表現が豊か
- 「階調が広い」と白飛び、黒つぶれに強い
- RAW現像で復活できたりする
- フルサイズは光を多く取り込めるから強い
- ダイナミックレンジの広さ、明暗差に強い
- 風景や夜間などの暗い所での撮影は強い
- 特にNikonの黒表現は個人的にも好み
- APS-Cでの夜景撮影は三脚やISO感度を意識
- もちろんフルサイズも丁寧に撮るのが理想

今回はたくさんあるセンサーサイズから、APS-Cを選ぶべき人の特徴と
選んだ際のメリット、デメリットをお伝えしました。
YouTubeでも熱量込めて解説しているので
是非、一緒に見てね(^^)